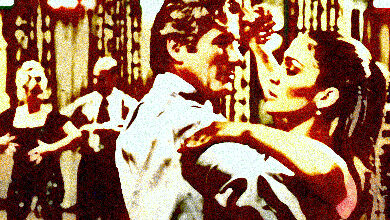母と妹を残し、ベトナムから日本へ出稼ぎに来たタンヤ。TANUKIという舌に乗せると望みの国籍者に変身できる違法薬物を服用して、日本人に化けてホテルで働いていた。同じホテルで働いている日本人の同僚とも親しくなり、日本の生活に馴染んでいくが、薬物の副作用により、徐々にタンヤは日本人の姿のまま本来のベトナム人の姿に戻れなくなっていく…。
(大まかなあらすじを紹介)
ぴあフィルムフェスティバルに出品された本作の紹介文の一部を抜粋すると、『在日外国人の生きづらい現実をおとぎ話として描いた異色作』とある。在日外国人にとって、なにが生きづらさにつながっているのか?
当然ながら、日本は現在、植民地支配や奴隷制度を政策としてとっているわけではない。外国から人間を首根っこつかまえて強制的に日本へ連れてきて働かせたり、外国人の文化や言葉を全面的に否定して同化政策を強いているわけでもない。技能実習制度が現代の奴隷制度だと批判されることはあるが、ニュースやネットで切り取られている暴行や人権無視に関するような悪しき動画は技能実習制度のほんの一部分の闇であり、メリットも多くあるからこそ、毎年何十万人と技能実習生が日本へやってくるのだ。
日本で中国語やベトナム語やシンハラ語を喋っていても、警察や市民からリンチにあうことはないし、外国人向けの食料品店も多く存在し、彼ら彼女らが何を食べても自由だ。信仰の自由も存在し、イスラム教の礼拝所を建設することも禁止していない。
日本において、ある程度の外国人の自由は保障されているはずだ。
日本へ来て、もし日本語を喋ったり、日本らしい接客ルールやマナーを守ることが『生きづらい』とされるならば、母国で生活していればいいことだ。日本人であったって、外国に住んでいればその土地の習慣や文化を尊重することは当たり前である。それらを『生きづらさ』の一言で片づけてしまうならば、それはわがままというものだろう。では、本作で『生きづらさ』が表現された場面はなかったのだろうか?
唯一、作中で具体的に表現されている箇所は、タンヤが和食料理屋のオープンキッチンで働いているシーン。彼女は一生懸命調理をして、出来上がった料理はなんの問題もなさそうな見た目をしているが、和服をきた年配女性の客から「外国人の作った料理は食べたくない。作り直して」と言われてしまう。接客をした同僚も、「申し訳ございません。調理しなおします」と、外国人が料理をすること自体が申し訳ないことなのだと、客への返答の仕方で肯定してしまう形をとる。
外国人という見た目による差別である。これはあきらかに差別だ。出された料理の見た目が崩れていたり、調味料を間違えて味が不味かったり、髪の毛や折れた割りばしが入っていて衛生状況や危険があればクレームが発生する余地はある。しかし、見た目にも申し分なく、衛生管理も守られていた上で、ただ外国人が作ったからというだけで文句を言うならば、作中の年配女性の主張していることは差別であり、ヘイトである。
この年配女性や料理屋の同僚が無意識にしていることは、実は多くの日本人がとる態度を象徴しているのではないか。外国人に対する無関心、外国人を見たくないという心理。つまり現在の日本が置かれている状況を理解していないのだ。なぜ、日本に外国人がたくさんいるのか、と。
作中のようなオープンキッチンではなくとも、飲食店の厨房では多くの外国人が働いているし、全国の農場や工場で多くの外国人が飲食料品製造の一翼を担っている。「外国人が作った食べ物を食べたくない」とのたまいながら、無意識に外国人の作った飲食料品をコンビニやスーパーで買って食べてもいる。これは矛盾というものだろう。いまや、外国人に働いてもらわなければ各産業の現場が回らない現実がある。
日本人も在日外国人も、日常生活を送る上で、どこまでが差別で、どこまでが守るべきルールやマナーなのか明確に線引きする必要はある。ゴミ出しの仕方や、公共空間での騒音問題などに関しては、ルールやマナーは守ってもらう必要がある。一方で、コンビニの前でたむろしているだけで怖い、というような見た目に基づく感情論は、論理的な理由がない差別である。
作中でさりげなく触れられた、『外国人というだけでアパートを借りるのが大変』問題。これは、不動産屋もビジネスでやっている以上、家賃を安定的に徴収できるのかという懸念があったり(日本人の高齢者に対しても同じ理由でアパートが借りづらい問題がある)、上記のようなゴミ出しの仕方や騒音による日本人住民とのトラブル、言語の壁等あり、感情論ではないはっきりとした理由があるため、差別ではない。
どんなに努力しても『外国人だから』と、見た目による差別をされてしまう。だからTANUKIを服用して日本人の見た目に変身するのである。どこまで行けば、日本の文化を尊重し、理解していることになるだろう。外国人の見た目のままでは受け入れられる余地はないのか。
現実社会では、言葉は努力して上達することができても、ベトナム人がベトナム人としての見た目を変えることはできない。見た目が日本人ではないというだけで差別されるならば、差別する日本人の考え方を改めなければならないだろう。プライドや価値観を守ることも必要だが、目まぐるしく変わっていく世界の潮流を見極めて、井の中の蛙でいるばかりでなく、変化していくことも重要だ。どの時代においても、変化することを止めることはできない。
監督のチェ・ユシン氏は、ほのぼのした作風が特徴の荻上直子監督のファンだそうである。作中にもコミカルなわらべうたのような音楽が流れるが、確かに荻上氏のイズムを感じる。作品の全体的な雰囲気とマッチしているかどうかは別だが…。